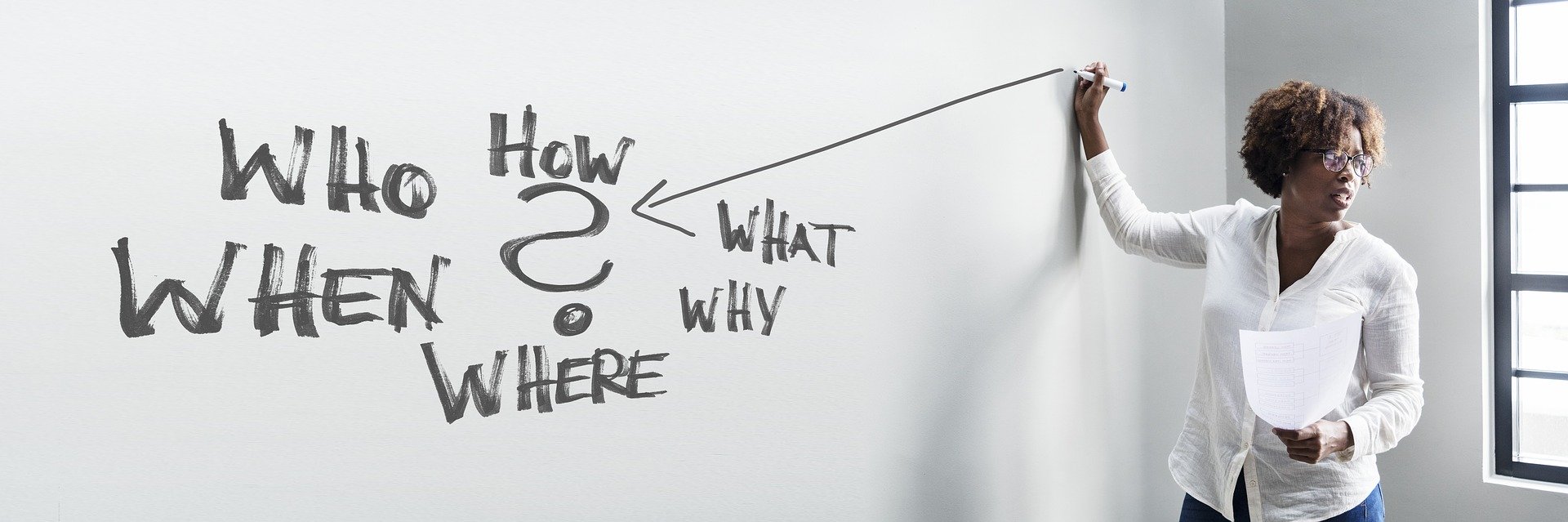営業マンが知っておくべき『Web3.0』
Web3.0はIT産業やデジタル産業・事業だけではなく一般企業の会社員や営業マンも知識として得ておかなければならない時代が来ています。
スマホをこの10年ほどでほとんどの人が使いこなせるようになり電子マネーを使うようになったように、Web3.0は生活に密接に関わります。
新聞やネットでブロックチェーンや暗号資産・仮想通貨、DX(デジタルトランスフォーメーション)という単語を身にしても理解しているのと知識や説明、応用ができるかでは大きな差があります。
まずWeb3.0は6つのポイントを押さえておく必要があります。
このWeb3.0の6つのポイントを営業マン目線で書いてみましたのでご参考ください。
1. 分散型の仕組み ユーザー主導のデータ管理
Web3.0は、中央集権的な制御から分散型の仕組みへの移行を象徴しています。これにより、ユーザーは自身のデータや取引を完全に管理でき、企業や中央機関の制御が難しくなります。営業マンは、顧客や自社がこの新しい自主管理していくようになると考えておく必要があります。
データセキュリティやプライバシーの価値はコンプライアンスなどにも関係するので必須の知識です。
2. ブロックチェーン技術 透明性とセキュリティの向上
Web3.0の基盤には、ブロックチェーンや分散台帳技術が使用されます。これにより、取引の透明性が向上し、セキュリティが確保されたデジタル取引が可能となります。営業マンは自社の商品や自社のブロックチェーン技術が用いられるようになってきます。
特に、金融関係は特に中央集権型で、他の事業でも分散型の権限を持つプラットフォームは少ないため、慣れが必要です。
3. 暗号通貨とスマートコントラクト 新たな取引手段の提案
Web3.0環境では、暗号通貨(例: ビットコイン、イーサリアム)とスマートコントラクト(自動的に契約を実行するプログラム)が支払いや取引の基盤として機能します。既に自社の取引が暗号資産や仮想通貨を利用している場合もあるでしょう。
元々、自販機や券売機のようなシステムを扱っていると理解はしやすいと思いますが、応用すればスマートコントラクトはさまざまな事業が扱うようになります。
これらの仕組みを理解し、顧客に対して新たな取引手段として提案する時代もすぐにくるはずです。
4. デジタルアセットの管理 ブロックチェーン上での所有権証明
Web3.0では、デジタルアセット(デジタルコンテンツ、仮想通貨、NFTなど)の所有権をブロックチェーン上で証明できます。
車検証や不動産登記書・保険証などもデジタル化が水面化で進んでいます。
現在は書面でやりとりしている営業マンは確実に所有権などの証明がデジタル化され、より安全に取引されることを理解しなければなりません。
それが『なぜ安全か』『なぜ利便性に長けているか』を具体的に情報提供する知識を必要とするでしょう。
5. セキュリティとプライバシー 安全な取引環境の確保
分散型の仕組みにおいてもセキュリティとプライバシーは重要です。営業マンは、平成中期から個人情報保護やプライバシーは知らないでは済まない時代になりました。顧客情報やデータを管理するのは鍵付きキャビネットという時代が今以上にセキュアな取引手段とプライバシー保護となります。
6. 新たなビジネスモデル 顧客との共創と新しい収益機会
Web3.0は、新しいビジネスモデルや収益機会を生み出す可能性を秘めています。営業マンは自社が『Web3.0』を関連させたシステムや商品を提供するのは自分には関係ない、まだ先の話で定年前だと思ったりすると、営業マンとしての居場所はなくなってしまうでしょう。
『Web3.0』を営業マンによりわかりやすく解説する
Web2.0が現在、『Web3.0』が今からの未来
Web1.0は一般的にYahoo!などで検索し情報を閲覧する時代でした。
Web2.0ではTwitterやFacebookなどのSNSやYouTubeのようなプラットフォームが登場し、専門知識がなくても情報発信がWEB上で可能になりインフルエンサーやYouTuberという仕事や職業、収益モデルが生まれました。
「Web2.0」は、現在進行形で利用していますが、「Web3.0」は未知のサービスや商品、作品や職業が生まれます。
現時点でもNFT作家などは少なくともWeb3.0の時代だと言えます。
そして相手を信じる・信じないというのも大きく変わるでしょう。
Eサイト・ECサイトでモノを買うにも、現在は知名度の高さが重要視されますし、実店舗でクルマなどを買うにしても印鑑証明や高額の頭金を預けられるか『信じられるかどうか』を個々が判断しなければなりません。
少なくとも「Web3.0」になれば、情報が細かく分散されるためハッキングや不正アクセスなどをしても得られるものが少ない状態のため、『信じられるかどうか』を個々に判断する必要がなくなると言えます。
営業マンが知っておくべき『Web3.0』の導入
2018年以降、日本では電気量販店などを皮切りに、徐々に仮想通貨や暗号資産を受け入れるお店が増加しています。例えば、ビックカメラ、コジマ、ソフマップなどの電気量販店では仮想通貨や暗号資産での支払いが可能です。また、日本発祥の仮想通貨であるモナコインは、パソコン販売店などで利用されています。
小売業界における仮想通貨や暗号資産の普及は、他の業種に比べてやや遅れています。例外として、メガネスーパーは仮想通貨や暗号資産による支払いを導入しています。しかし、この取り組みが企業の売上にどの程度貢献しているのか、また利用者の利便性向上にどれだけ寄与しているのかという点については疑問が残ります。
現状、仮想通貨や暗号資産を利用できるお店は、その利用に興味を持っている一部の人々にしか広まっていません。このような支払い方法の普及を促進するためには、普及啓発活動や利用者の安心感を高めるセキュリティ対策などが必要とされています。
他にも『ジェムキャッスルゆきざき』という高級腕時計販売店も実は早くから仮想通貨・暗号資産での支払いができることで有名です。
『ジェムキャッスルゆきざき』は2018年年始からビットコイン決済を全店舗で導入し、その後ビットコインキャッシュ(BCH)、そしてイーサリアム(ETH)での支払いが可能です。
営業マンが知っておくべきWeb3.0とNFTの市場規模
Web3.0の国内市場規模は、現在約929億円と言われ、2030年には世界で815億米ドルに達すると予想されています。
NFTに関しては今後5年間で10.32%成長し1,025億円に達すると予想され全体として10.32%の成長と予測しています。
NFTを仮にアートだけで括り考えても一般美術市場は約5兆円〜6兆円規模ですが、NFT市場では既に4.7兆円以上になっています。
2021〜2023年で100倍を超えています。
NFTとは?
営業マンやビジネスマンが勘違いするWeb3.0の関連ワード
Web3.0へ移行することで登場するキーワードとして、
- NFTとWeb3.0
- dAppsとWeb3.0
- 暗号資産とWeb3.0
- ブロックチェーンとWeb3.0
- DeFiとWeb3.0
- スマート・コントラクトとWeb3.0
と常に同じ意味ではなく混同されます。
関連性のある言葉で極めて近い意味合いがある部分もありますがWeb3.0を目指すため・維持していくために必要・利用・活用されるということを前提にとWeb3.0は勉強していく必要があります。
例えば『暗号資産とWeb3.0』を知っているから『NFT』や『DeFi』 の勉強をしなくていいとはならず包括的に、学ぶ必要があります。
Dappsとは?
Dappsは、Decentralized Applicationsの略で、読み方はダップスと呼称されています。
Dappsは分散型アプリケーションと日本語では解釈され、ブロックチェーンの特性を活かして、ユーザーデータ(個人情報や顧客データ)を企業が管理するのではなく、必要に応じて引き込むことで、情報漏洩などのリスクヘッジに役立てることができます。
DeFiとは?
DeFi(Decentralized Finance)は経済紙やネットの言葉を用いると『中央管理者を必要としない分散型金融』のことです。
ここでの中央管理者というのは中央銀行や政府機関をイメージしてもらうと、銀行を必要としないで銀行が行っているサービスが受けられるということです。
中央銀行や政府機関はDeFiの反対語でCeFi(=Centralized Finance)の略です。
CiFiが分散型金融に対して『中央集権金融』を表します。
顧客や取引先が気にしている『Web3.0』事情
ビットコイン・仮想通貨投資の節税・税金対策はあるのか
営業マンが雑談や契約・取引・商談で気にしているのは節税対策や税金対策になるか、という点です。
この部分を営業マンが知っているだけで話題を引っ張ることができます。
雑談や契約・取引・商談で気にしているのは節税対策や税金対策になるか、という点の答えだけを言えばマイナンバー制度の普及で申告漏れや申告逃れは確実に分かるようになっています。
暗号資産交換業所・取引所は国税庁から情報開示をしないということは期待できず、海外の交換業者を利用している場合は特に実は、確認対象項目を増やす理由付けがしやすくなるため『所得隠し』として悪意性を持って調査されるため注意が必要です。
「税金は逃げ道がないよな」と言われた時、一言言えるのは「保有し続けるのが一番賢明かもしれませんね」と続けることができます。
『Web3.0』で節税・税金対策は保有し続けること
仮想通貨・暗号資産の税金対策・節税で唯一得策だと言えるのは、安い時に買ってホールドし続けることです。
暗号資産を保有し続けるというゴールドなどの現物投資と同様に、どれだけ価値が上がっても、日本円やドルなどの法定通貨や別の仮想通貨・暗号資産に換金しない限り課税対象(=非課税)となりません。
そのため、仮想通貨・暗号資産は保有し続けていれば節税になる可能性が十分にあります。
逆に売買をこまめにして利確してしまうと所得となるため、暗号資産は総合課税であるため所得額を確定させるほど納税額は増えることになります。
*所得が大きくなるほど税率が上がる累進課税で、最高で45%(住民税・復興特別所得税を含めると約55%)の所得税が課されます。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円を超え 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
(参考データ引用元:国税庁ホームページ )
『金融リテラシー低い営業マンは今後どうすればいいのか』
この記事を読んで、そもそも金融リテラシーが低いと実感し危険やリスクを感じ『今後どうすればいいのか』、言い換えれば「助けてくれよ」と思った方もいるはずです。
しかし。金融リテラシーが低い場合、できることは意識的に金融リテラシーを向上させるしか方法はありません。
これは積み重ねだけでできることで頭の良さや記憶力・資格や学歴の有無は関係ありません。
だからこそ、自己啓発と学習、専門家の相談、リスク管理、健全なマネーマネージメント、不要な借金の避け、SNSやマーケティングの注意、公的制度や投資機会の活用など少しずつ目を背けずやっていくしかないのです。